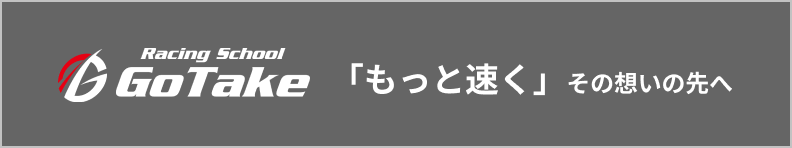日産レーシングスクールから開発ドライバーへ
青木選手はレーサーとしての未来を切り拓くべく、プロ養成機能を持った日産レーシングスクール(現:NISMOドライビングアカデミー)を受講する。当時は和田孝夫氏、星野一義氏、長谷見昌弘氏といった日産を代表するワークスドライバーが審査員を務めていた。
スクールの最優秀生には、プロへの道が開かれる検定会が用意されていた。青木選手は2回目の受講で最優秀成績をおさめ、検定の機会を獲得。ディーラー勤務で培ったメカニズムへの造詣や、得意とするブレーキング技術が活きて見事合格した。そしてこれがキャリアを飛躍させるきっかけになった。
検定では「翌年は何かがある」と聞かされていた。それは日産のレーシングカー開発だった。神奈川県の追浜やSUGOでのレース車両の開発は、資金繰りに苦労しながらレースを続けていたキャリアを激変させた。

「とにかく長い距離をレーシングカーで走れました。また開発部隊に入るとたくさんの最新技術を試せます。セッティングも教えてもらうことができました。SUGOをたくさん走っていたこともGTのチャンスをもらえた理由だったかもしれません」
1997年には日産開発部隊の覆面チーム「まんぷく堂」でスーパー耐久に参戦。仕事をレースに捧げる日々から職業レーサーになったのは、26歳で迎えた1998年。開発部隊からのアサインでJGTCのシートを獲得したときだった。それまでのFJ1600、F4、スーパーN1耐久(現:スーパー耐久)は参戦資金を自分で持ち込んでいた。青木選手は当時を「趣味が仕事になり、人生が変わった」と振り返る。

プロレーサーとして活躍を始める
1998年、「Best Motoring」などビデオの世界だったJGTCが。青木選手の主戦場になった。当時ドライバーとして参戦していた近藤真彦選手とタッグを組み、NISMO契約でザナヴィシルビアを駆った。それから四半世紀以上にわたってトップレーサーとして君臨する上での立ち居振る舞いは、「マッチ」から授かったという。

しかし、シーズン終了後にチームプロジェクトの終了が青木選手を襲った。NISMO契約を失い、関係者から「連絡するから待っていて」と告げられるも連絡は来ない。1999年シーズンが始まり「待っていてはダメだ!」と必死にシートを探す。シーズン途中でようやく、以降複数シーズンを共にするDAISHINに滑り込んだ。
「それでもそのシーズンが終わると本当に何のシートもなくなってしまいました。近藤さんに連絡し、鈴木亜久里さんに口利きをしてもらうことで、1999年から始まったフォーミュラ・ドリームに参戦できました。『初年度はチャンスがある』と感覚的にわかっていたんです」


同年は毎週DAISHINに足を運んで「GTに乗りたい」と言い続け、獲得した鈴鹿1000km GT300クラスのシートでクラス優勝の実績を残す。その結果が評価され、翌年からはDAISHINレギュラードライバーの座を掴んだ。
同チームで迎えた2001年。チームのシルビアは戦闘力に勝り、2度の優勝を挙げてシリーズチャンピオンに輝いた。今でもキャリアを通して最も印象に残っているとは言いつつも、青木選手はチャンピオン争いそのものには無頓着だったという。
「僕は目の前のレースにものすごく集中するので、今でもシリーズポイントは意識していません。当時も『何位以上ならチャンピオン』という話は聞いていましたが、最終戦のひとつ前のレースでチャンピオンの可能性があったことも知りませんでした」